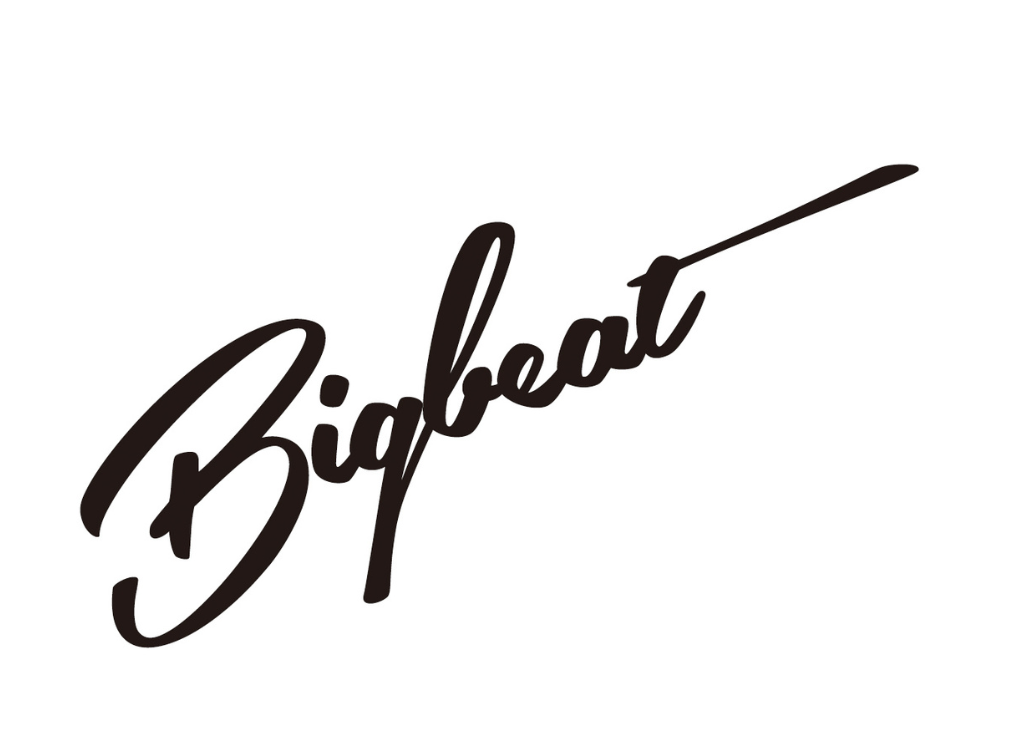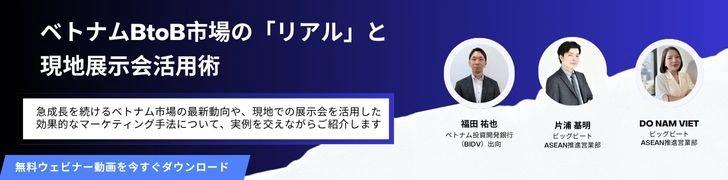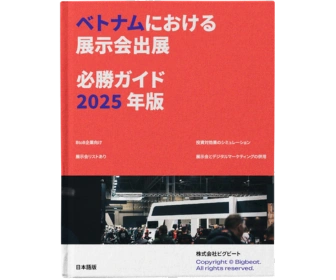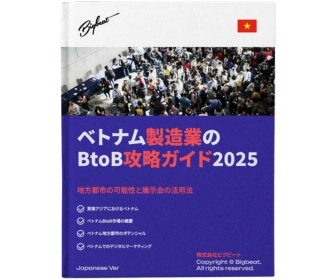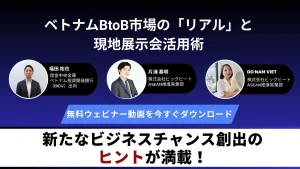ベトナムとタイは、共にASEAN経済圏において重要な位置を占める国々ですが、ビジネス環境や投資機会において大きな違いがあります。2025年現在、多くの日本企業がASEAN地域への進出を検討する中で、この2カ国は特に注目を集めています。本記事では、ベトナムとタイの経済成長率、政治体制、外資誘致政策など様々な側面から徹底比較し、最適な進出先を選ぶための重要な情報を紹介します。
ベトナムとタイの基本情報と経済状況の違い
両国は同じASEAN地域にありながら、経済発展段階や成長性において異なる特徴を持っています。まずは基本的な経済指標から見ていきましょう。
経済成長率と将来予測
ベトナムは2025年〜2030年にかけて、実質GDP成長率が年平均6.5〜7.0%と高水準で推移する見通しです。これはASEAN諸国の中でもトップクラスの成長率であり、長期的な成長投資先として高い魅力を持っている点が特徴的です。
一方、タイは成熟段階に入りつつある経済で、近年は成長率が鈍化傾向にあります。特に自動車産業や食品加工など従来の主力製造業において、一部景況感の悪化が見られます。しかし、経済基盤の安定性や高度な産業インフラは依然として強みとなっています。
市場規模と消費者特性
ベトナムは約9,800万人の人口を有し、若年層が多いことが特徴です。平均年齢は31歳前後で、消費意欲が高く、デジタル技術への適応も早いため、新しいサービスやビジネスモデルを導入しやすい市場となっています。
タイの人口は約7,000万人で、ベトナムより少ないものの、一人当たりGDPはベトナムの約2倍以上となっています。中間層・富裕層の形成が進んでおり、高品質な製品・サービスへの需要が高まっています。プレミアム市場を狙うビジネスにとって魅力的な消費者層が存在する点が強みです。
主要産業構造の違い
ベトナムでは電子機器製造、繊維・衣料品、建設業などが主力産業となっています。特に電子部品や製品の製造拠点としての地位が急速に向上しており、サムスンやインテルなどグローバル企業の大規模生産拠点が設立されています。
タイは自動車産業を中心に、食品加工、電子機器製造などが主要産業です。特に自動車産業はASEAN地域における一大拠点となっており、「アジアのデトロイト」とも呼ばれています。しかし、電気自動車(EV)への移行期にあり、産業構造の転換が進行中です。
政治体制と外資政策の違い
進出先を選ぶ際に重要となるのが、政治体制の安定性と外資に対する政策です。両国はこの点でも大きく異なる特徴を持っています。
政治体制と安定性の比較
ベトナムは共産党による一党支配体制を敷いています。この政治体制により、政権交代による政策変更リスクが小さく、中長期的な政策運営が継続的に行われる傾向があります。企業からみた政策の予測可能性と安定性が高いことが、外国企業にとって大きなメリットとなっています。
一方、タイは立憲君主制のもとでの民主主義体制を採用していますが、過去には軍事政権への移行やクーデターなど政治的な不安定要素も存在しました。2025年現在は政治的な安定を取り戻しつつありますが、政策の変更リスクはベトナムと比較すると相対的に高いと言えます。
外資誘致政策と投資環境
ベトナムでは外国直接投資(FDI)の誘致に積極的で、2025年前半だけでも67億米ドル超の投資を記録しています。投資インセンティブも充実しており、製造業や輸出産業に対する法人税の減免、土地使用料の免除など、外資企業に有利な条件を提供しています。
タイも「タイランド4.0」と呼ばれる産業高度化政策のもと、先端技術産業や高付加価値産業への投資を積極的に誘致しています。特に東部経済回廊(EEC)地域では、投資恩典や税制優遇措置が拡充されています。高度技術を持つ企業や研究開発拠点としての進出に有利な環境が整っている点が特徴です。
法制度と行政手続きの透明性
ベトナムでは近年、ビジネス環境改善のための法制度整備が進んでいますが、行政手続きの透明性や予測可能性については依然として課題が残されています。地方によって解釈が異なることもあり、現地パートナーや専門家との連携が重要となります。
タイは比較的整備された法制度を持ち、行政手続きも透明性が高いとされています。特に投資委員会(BOI)による一元的な窓口対応など、外資企業の進出をサポートする体制が構築されています。ただし、外資規制や外国人事業法による業種制限は依然として存在します。
労働環境と人材の違い
事業運営において欠かせない労働力の質と量は、両国で大きく異なります。それぞれの特徴を理解し、自社のニーズに合った選択をすることが重要です。
労働人口と賃金水準
ベトナムの労働人口は約5,500万人で、平均賃金は製造業の工場労働者で月額300〜500ドル程度です。若年層が多く、労働力の供給が豊富であることが特徴で、労働集約型産業にとって有利な環境を提供しています。特に近年は教育水準の向上により、技術系人材の質も向上しています。
タイの労働人口は約4,000万人、平均賃金は製造業の工場労働者で月額450〜700ドル程度とベトナムより高めです。少子高齢化が進みつつあり、労働力不足が一部産業で課題となっています。その一方で、製造業の経験が豊富で、技術力の高い人材が多い点が強みです。
教育水準と技術スキル
ベトナムは理数系教育に力を入れており、特にIT人材の育成に注力しています。プログラミングスキルを持つ若手技術者が増加しており、デジタル分野での人材供給が充実しつつあります。しかし、高度な技術や管理能力を持つ中間管理職層はまだ不足している状況です。
タイは製造業の長い歴史を持ち、技術者や熟練工の層が厚いことが特徴です。高等教育も充実しており、エンジニアリングや経営管理のスキルを持つ人材も多く、高度な製造プロセスや品質管理を要する産業に適した人材が豊富です。
労働法制と雇用慣行
ベトナムの労働法は労働者保護の色合いが強く、解雇規制も厳しい傾向にあります。最低賃金は地域によって異なり、毎年見直されています。労働組合の活動も活発で、ストライキなどの労働争議が発生することもあります。
タイの労働法も同様に労働者保護の傾向がありますが、企業側の柔軟性もある程度確保されています。雇用慣行は日本に近い部分もあり、長期雇用を前提とした人材育成が可能です。ただし、転職率は日本より高く、優秀な人材の確保・維持には競争力のある待遇や職場環境の整備が求められます。
ベトナムとタイのインフラと物流環境の違い
製造業や流通業にとって重要なインフラと物流環境においても、両国には明確な違いがあります。ビジネスモデルに合わせた選択が必要です。
交通インフラの整備状況
ベトナムのインフラ整備は急速に進んでいますが、依然として発展途上の面があります。主要都市間を結ぶ高速道路網は拡大中ですが、地方部の道路インフラは整備が遅れている地域もあります。ホーチミン市やハノイなど主要都市では都市鉄道の建設も進んでいます。
タイは東南アジア地域内でも優れた交通インフラを有しています。高速道路網が整備され、バンコクを中心に鉄道網も発達しています。物流の効率性と信頼性が高く、ASEAN域内物流のハブとしての役割を担っている点が大きな強みです。
工業団地と産業集積
ベトナムでは全国各地に工業団地が整備されており、特に南部のビンズオン省や北部のバクニン省、バクザン省などに多くの製造業が集積しています。ビンズオン省は家具や繊維産業が盛んで、中小企業にも適した環境を提供しています。バクニン省は電子機器製造の拠点として発展し、バクザン省は近年急速に工業化が進む地域です。
タイでは東部経済回廊(EEC)を中心に先端産業の集積が進んでいます。特に自動車産業の集積は東南アジア最大規模で、関連部品メーカーのエコシステムが確立されています。また、バンコク周辺にも多くの工業団地があり、産業クラスターの形成によるサプライチェーンの効率化が図られている点が特徴です。
電力・通信などのインフラ整備状況
ベトナムの電力供給は急速な経済成長に伴う需要増加により、一部地域では安定性に課題があります。工業団地では自家発電設備を持つところもありますが、電力コストは比較的低く抑えられています。通信インフラは都市部を中心に整備が進み、インターネット普及率も急速に向上しています。
タイの電力インフラは比較的安定しており、停電のリスクは低いです。ただし、電力コストはベトナムより高い傾向にあります。通信インフラも充実しており、デジタル技術を活用したビジネスにも適した環境が整っています。水資源の管理も進んでおり、工業用水の確保も比較的容易です。
事業コストと税制の違い
ビジネスの収益性に直結する事業コストと税制面でも、両国には特徴的な違いがあります。長期的な視点での検討が重要です。
法人税率と税制優遇措置
ベトナムの標準法人税率は20%ですが、優遇地域や優先産業には大幅な税制優遇措置があります。特に輸出志向の製造業や先端技術産業では、最長4年間の法人税免除と続く9年間の半減措置が適用される場合もあります。特定地域の工業団地では更に優遇措置が厚くなることもあるのが特徴です。
タイの標準法人税率は20%で、投資委員会(BOI)の認可を受けた事業には最長8年間の法人税免除などの優遇措置があります。特に東部経済回廊(EEC)地域や研究開発、イノベーション関連の事業には手厚い優遇措置が適用されます。ただし、適用条件が詳細に規定されており、申請手続きもやや複雑です。
土地・施設コスト
ベトナムの工業用地は地域によって大きく異なりますが、ホーチミン市やハノイ近郊の工業団地では1平方メートルあたり100〜150ドル程度です。地方に行くほど安価になり、オフィス賃料もバンコクと比較して2〜3割程度安い傾向にあります。
タイの工業用地はバンコク周辺や東部経済回廊で1平方メートルあたり200~300ドル程度と、ベトナムより高めです。しかし、インフラの整備状況や利便性を考慮すると、コストパフォーマンスは依然として高いと言えます。オフィス賃料もASEAN地域では中程度の水準です。
その他の運営コスト
ベトナムでは電力コストが比較的安く、kWhあたり7~9セント程度です。水道料金も安価ですが、安定供給の面では地域差があります。通信コストも低めで、特にデジタル関連のサービス運営には有利な環境といえます。
タイの電力コストはkWhあたり10~12セント程度とベトナムより高めですが、安定した供給が魅力です。水道料金も適正で、品質も安定しています。全体的に見ると、ベトナムより運営コストは高めですが、インフラの安定性や事業環境の確実性を考慮すると、特に高品質な製品製造には適した環境といえます。
市場特性と消費者動向の違い
内需を狙った市場参入を検討する場合、両国の市場特性や消費者動向の違いを理解することが重要です。人口構成や所得水準、消費行動には大きな違いがあります。
小売市場とEコマースの発展状況
ベトナムの小売市場は伝統的な市場(ウェットマーケット)から近代的なショッピングモールやコンビニエンスストアへの移行が進んでいます。特に都市部では、イオンモールなどの大型商業施設が人気を集めています。Eコマース市場も急速に拡大しており、Shopee、Lazada、Tiki、Sendo などのプラットフォームでの競争が激化しています。2025年のEコマース市場規模は約200億ドルに達すると予測されています。
タイの小売市場はより成熟しており、セントラルグループやモールグループなどのローカル企業が強い影響力を持っています。コンビニエンスストアの普及率も高く、セブン-イレブンやファミリーマートが全国に展開しています。Eコマース市場もベトナムより先行して発展しており、2025年の市場規模は約350億ドルと予測されています。Shopee、Lazadaに加え、JDセントラルなどのプラットフォームが活発に事業展開しています。オムニチャネル戦略の重要性が高まっている点も特徴です。
ビジネス商習慣と文化的な違い
ベトナムのビジネス文化は、人間関係を重視する傾向があります。初めての取引では、信頼関係の構築に時間をかける必要があるでしょう。また、儒教的な価値観が根強く残っており、年長者や地位の高い人への敬意を示すことが重要です。意思決定プロセスはトップダウン型が多く、最終決定には時間がかかることがあります。
タイのビジネス文化は、「マイペンライ(気にしないで)」という言葉に象徴されるように、柔軟性と調和を重んじる特徴があります。対立を避ける傾向が強く、交渉では「Win-Win」の関係構築を目指すアプローチが効果的です。また、王室への敬意は非常に重要であり、ビジネスの場でも王室に関する配慮が必要です。日系企業との取引経験も豊富で、日本的なビジネス慣行への理解も比較的高いと言えるでしょう。
進出日系企業の動向
両国における日系企業の進出状況や最新動向を把握することで、自社の戦略立案に役立つ情報が得られます。
業種別の進出状況
ベトナムへの日系企業進出は、製造業が中心で電子部品・デバイス、繊維・衣料、食品加工などの分野が多くを占めています。近年ではITサービス業やBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)などのサービス業の進出も増加傾向にあります。製造からサービスまで幅広い業種が新たなビジネスチャンスを見出している点が特徴です。
タイでは自動車・同部品メーカーの進出が最も多く、次いで電気・電子機器、化学・医薬品などの分野が続きます。近年では、研究開発拠点の設立や地域統括拠点としての機能強化など、高付加価値領域での事業展開が目立ちます。また、タイを拠点として周辺諸国(カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム)への展開を図る企業も増えています。
最新の投資動向とトレンド
ベトナムでは、米中貿易摩擦の影響もあり、中国からの生産移管を目的とした投資が増加しています。特に電子機器関連の製造業の動きが活発で、サプライチェーンの多様化・リスク分散の観点からの投資が目立ちます。また、急速に拡大する国内市場をターゲットとした投資も増えており、特に食品、小売り、金融サービスなどの分野での進出が増加しています。
タイでは、自動車産業の電動化に対応するための投資が活発化しています。電気自動車(EV)関連の部品製造や、次世代モビリティサービスなど新たな分野への投資が増えています。既存産業の高度化と新産業への転換を同時に進めている状況が見られます。また、デジタル技術を活用したスマート工場化など、製造プロセスの高度化に向けた投資も増加しています。
事業展開における課題と対応策
ベトナムでの事業展開における主な課題としては、中間管理職層の人材不足、行政手続きの不透明さ、突然の法制度変更などが挙げられます。これらの課題に対応するため、多くの日系企業は現地人材の育成強化、現地コンサルタントやパートナーとの連携強化、業界団体を通じた情報収集や当局との対話強化などの対策を講じています。
タイでの事業展開では、人件費の上昇、労働力不足、産業構造の転換に伴う事業環境変化などが課題となっています。これに対し、生産プロセスの自動化・効率化、高付加価値製品・サービスへのシフト、研究開発機能の強化などの対応が進められています。また、タイを拠点としながらも、一部工程を周辺国に移管するといった地域最適化戦略も採用されています。
ベトナムとタイへの進出戦略の選び方
これまでの比較を踏まえ、自社の状況や目的に合わせた最適な進出先と戦略を選ぶためのポイントを解説します。
業種別の最適進出先
製造業の中でも、労働集約型の産業(繊維・衣料、組立加工など)はベトナムが有利です。豊富な労働力と比較的低い人件費を活かせるため、コスト競争力が重要な製品カテゴリーに適しています。また、急速に発展するITサービス業やBPOなどのデジタル関連事業もベトナムの若い人材と親和性が高いです。
一方、高度な製造技術や品質管理が求められる産業(自動車部品、精密機器など)はタイでの事業展開が適しています。熟練した技術者の存在や整備されたサプライチェーンを活用できる点が強みです。また、研究開発機能や地域統括拠点としての役割を担う場合も、ビジネスインフラが整ったタイが選ばれることが多いです。
進出形態の選択肢と判断基準
ベトナム進出の形態としては、100%外資の現地法人設立が比較的容易な分野が多く、製造業や輸出型産業では独資での進出が一般的です。一方、小売りやサービス業など一部分野では出資比率制限があるため、合弁会社形態が選ばれることもあります。初期投資を抑えたい場合は、ローカルパートナーとの業務提携や駐在員事務所の設立から始めるケースもあります。
タイ進出では、外国人事業法による業種規制があるため、多くの非製造業分野では合弁会社形態を取ることが一般的です。製造業でもBOI(投資委員会)の認可を受けることで100%外資の現地法人設立が可能ですが、認可条件や投資規模要件を満たす必要がある点に注意が必要です。中小企業の場合、現地代理店の活用や技術提携などのローリスクな形態から段階的に進出するケースも多いです。
中長期視点での進出先選定のポイント
中長期的な視点での進出先選定においては、以下のポイントを総合的に検討することが重要です。
まず、自社のビジネスモデルと市場特性の親和性を評価します。ベトナムは成長市場であり、新規参入の余地が大きい一方、タイは成熟市場で差別化が求められます。次に、サプライチェーン全体での最適化を考慮し、調達先や販売先との距離感も重要な判断材料となります。
また、人材戦略の観点からも検討が必要です。ベトナムでは若手人材の採用と育成が中心となり、タイでは既存の熟練人材の活用が中心となります。さらに、自社のリスク許容度に応じた判断も重要で、政治リスクや為替リスク、法制度変更リスクなどを総合的に評価する必要があります。
いずれの国を選択する場合も、現地視察や展示会参加を通じた生の情報収集が不可欠です。また、JETRO(日本貿易振興機構)や現地日本商工会議所、専門コンサルタントなどの支援機関を積極的に活用することで、より的確な判断が可能になります。
まとめ
本記事では、ベトナムとタイのビジネス環境について、経済状況、政治体制、労働環境、インフラ、コスト面など多角的に比較してきました。両国はASEAN地域の中で重要な投資先ですが、それぞれ異なる特徴と優位性を持っています。
- ベトナムは高い経済成長率、豊富な若年労働力、低コスト環境が強みで、製造拠点や成長市場開拓に適している
- タイは安定したインフラ、熟練技術者の存在、ASEAN域内物流ハブとしての機能が強みで、高品質製造や地域統括拠点に適している
- 業種や事業目的によって最適な進出先は異なるため、自社のビジネスモデルや戦略に合わせた選択が重要
- 長期的な視点でリスクと機会を評価し、段階的な進出戦略を検討することが成功のカギ
進出先の選定や海外展開戦略の策定には、専門的な知識と現地情報が欠かせません。株式会社ビッグビートは、海外展示会出展のサポートをしています。特に、タイやベトナムに現地法人を有しており、出展企画の立案から展示ブースの設営、コンパニオンをはじめとする運営スタッフの手配や管理に至るまで、日本の高い品質基準を維持したまま、現地からの迅速なサポートを提供することが可能です。ぜひご相談ください。