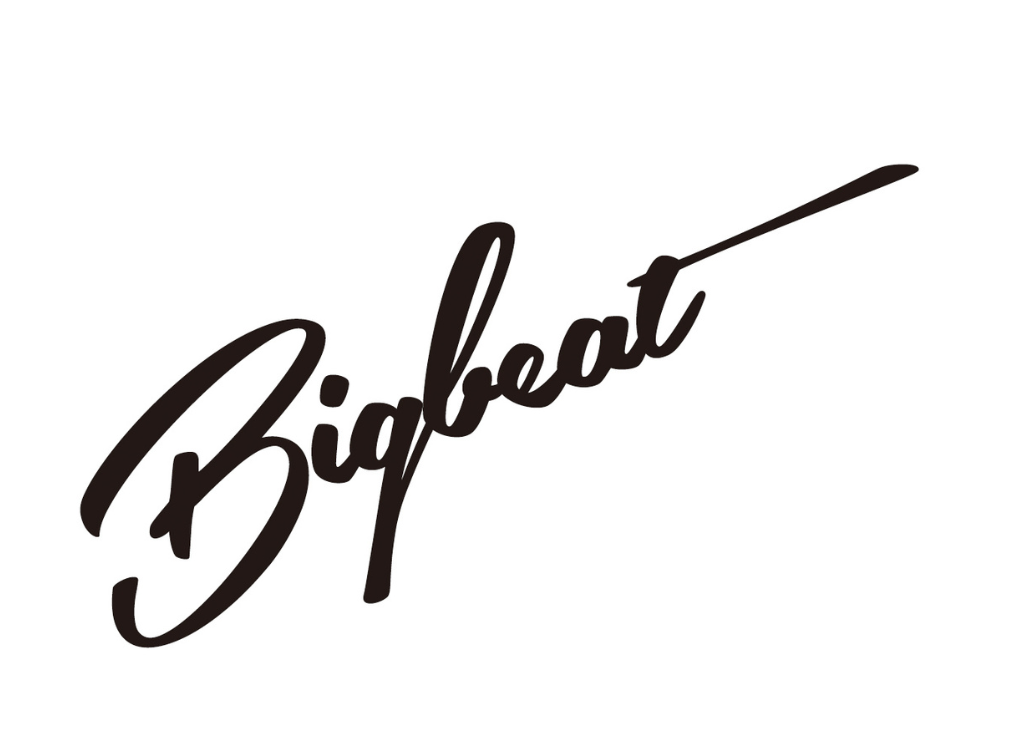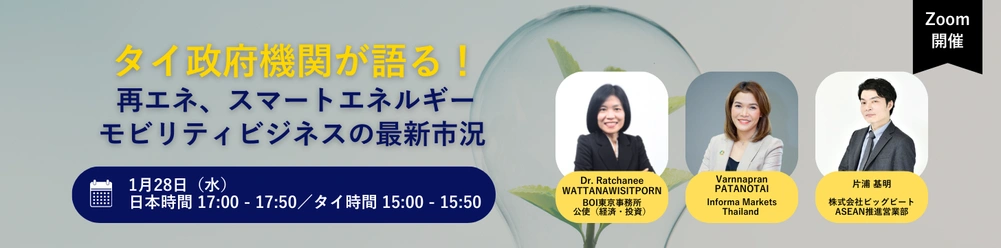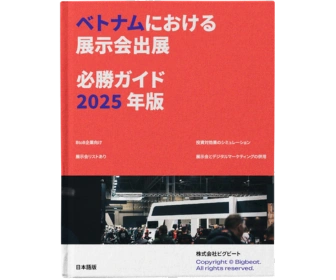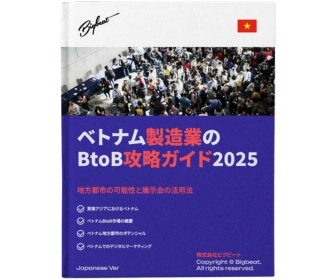ベトナムでは東南アジアの製造拠点として日本企業の進出が加速していますが、法規制の複雑化や人材確保の困難など、多くの課題が存在しています。特に2025年には企業法や関税法などの重要法律が改正され、ベトナム進出を検討する企業にとって最新の法規制への対応が不可欠となっています。本記事では、ベトナム進出における主要な課題を法規制・人材確保・その他のビジネスリスクの観点から徹底解説し、成功するための具体的な対策をご紹介します。
ベトナム進出時の法規制対応に関する課題
ベトナムへの進出において最も影響の大きい課題が法規制の理解と対応です。2025年の法改正により、従来の進出方法では対応できない新たな規制が導入されています。
企業法改正による受益所有者の登録義務
2025年の企業法改正により、受益所有者(実質的支配者)の登録義務が明確化されました。この改正は、企業の透明性を高める目的で導入されたものです。
受益所有者とは、企業の株式を25%以上保有する個人、または実質的に企業を支配している個人を指します。これまでグレーゾーンとされていた名義借り投資についても、新法では明確に禁止され、違反企業には企業設立拒否や営業停止処分が科される可能性があります。
さらに、外国人出資制限の強化も同時に実施されており、特定業種における外資規制の監視が厳格化されています。マネーロンダリング防止措置も強化されており、金融取引の透明性確保が求められています。
投資法改正による事業登録制度の複雑化
ベトナムの投資法は頻繁に改正され、事業登録制度も複雑化しています。進出形態の選択から実際の登録手続きまでにおいて、多くの企業が困難を感じているのが現状です。
現地法人設立、駐在員事務所設置、合弁会社設立など、それぞれの進出形態で必要な手続きや規制内容が異なります。特に外資規制の対象業種では、現地パートナーとの提携が必須となる場合が多く、パートナー選定の重要性が高まっています。
また、投資ライセンスの取得には平均3〜6ヶ月を要し、業種によってはさらに長期化する可能性があります。こうした状況から、事前の綿密な準備と現地の法務専門家との連携が成功の鍵となります。
関税法改正によるOn-the-Spot制度運用の不透明化
2025年の関税法改正では、長年グレーゾーンとされていたOn-the-Spot制度(みなし輸出入)が初めて法律上明記されました。この制度は、国内での取引であっても、特定の条件を満たすことで輸出入とみなされるものです。具体的には、この制度は、外国企業がベトナム国内の製造業者に原材料を支給し、完成品を引き取る取引形態などがこれに該当します。
従来は運用面での対応が曖昧でしたが、今回の法改正により制度の基本的な枠組みが確立されました。ただし、詳細な運用ルールについては今後発行される政令や通達を随時確認する必要があり、継続的な情報収集が必要となります。
この制度を活用することで、製造コストの削減や物流効率の向上が期待できる一方、税務処理や在庫管理の複雑化というデメリットも存在します。
ベトナム進出における人材確保と育成の課題
ベトナム進出における人材面での課題は、単純な人手不足ではなく、質の高い管理者層や専門人材の確保の困難さにあります。急速な経済成長に伴い、人材市場の競争が激化しています。
深刻な管理者層の人材不足
ベトナムでは一般労働者の人口は豊富ですが、マネジメント層となる中間管理職の人材が深刻に不足しています。特に日本企業の管理手法に精通した人材は極めて希少な存在です。
多くの日系企業では、現地拠点の管理を日本人駐在員が担っているのが現状です。しかし、駐在員のコストは現地採用の数倍に上るため、長期的な事業運営を考えると現地人材の管理者層への登用が不可欠です。
現地スタッフのマネジメント能力向上には、体系的な研修プログラムの構築と継続的な人材育成投資が必要です。日本本社での研修機会の提供や、段階的な責任範囲の拡大などの施策が効果的とされています。
即戦力人材の獲得競争激化
ベトナムの人材市場では、経験豊富な即戦力人材への需要が集中しており、獲得競争が激化しています。特に日本語能力を持つ人材や、特定の技術分野に精通した専門人材は慢性的に不足しています。
優秀な人材の獲得には、競争力のある待遇の提供が必要です。基本給だけでなく、住宅手当、交通費、健康保険、退職金制度など、ベトナムの労働法に準拠した包括的な福利厚生制度の構築が人材確保の成功につながります。
また、キャリア開発の機会提供も重要な要素です。昇進の可能性や技術習得の機会を明確に示すことで、優秀な人材の関心を引くことができます。
現地スタッフの離職率
ベトナムでは転職に対する抵抗感が低く、より良い条件を求めて転職する文化が根付いています。そのため、現地スタッフの離職率の高さが多くの日系企業の悩みとなっています。
定着率向上のためには、単純な賃金上昇だけでなく、働きがいのある職場環境の構築が重要です。従業員の意見を聞く仕組みづくりや、公平な評価制度の導入が効果的とされています。
さらに、ベトナムの文化的背景を理解した人事施策の実施も必要です。家族を大切にする文化的特徴を踏まえ、ワークライフバランスを重視した働き方の提供が従業員満足度向上につながります。
コンプライアンスとガバナンス体制の課題
ベトナム進出において日本企業が特に注意すべき課題は、コンプライアンス意識の違いとガバナンス体制の構築です。文化的背景の違いから生じるリスクへの対策が重要となります。
現地スタッフのコンプライアンス意識
ベトナムでは、日本と比較してコンプライアンスに対する意識が異なる場合があります。これは個人の資質の問題ではなく、教育制度や社会環境の違いに起因するものです。
不正行為や規制違反のリスクを最小限に抑えるためには、定期的なコンプライアンス研修の実施が不可欠です。研修内容は、日本の企業文化や価値観を一方的に押し付けるのではなく、なぜそのルールが存在するのか、守ることでどのような価値が生まれるのかを理解してもらうアプローチが効果的です。
具体的な事例を用いた実践的な研修や、現地の法律と日本の法律の違いを明確に説明することで、スタッフの理解度向上を図ることができます。
内部監査体制の不十分さ
ガバナンス体制が欠如している場合、特に財務処理、契約管理、人事管理の各領域において、適切なチェック機能が機能せず、リスクが高まります。内部監査体制が不十分であると、企業の業務運営における重要な問題が見過ごされ、信頼性の低下や法的リスクを招く可能性があります。
このような状況を改善するためには、現地スタッフのみならず、日本本社からの定期的な監査を組み合わせることが重要です。これにより、監査結果の透明性が高まり、発見された問題点に対して迅速かつ適切な改善措置を講じることが、企業の信頼性維持につながります。
さらに、内部通報制度の整備も不可欠です。現地スタッフが安心して問題を報告できる環境を整えることで、早期に問題を発見し、迅速に解決することが可能となります。
法改正に対応できる法務知識と専門人材の不足
ベトナムの法制度は複雑で、かつ頻繁に変更されるため、自社のみでの対応には限界があります。さらに、現地では信頼できる法律専門家が限られており、適切な人材を見つけること自体が容易ではありません。
法務専門家を選定する際には、単に法的知識があるだけでなく、日系企業のビジネス慣行を理解していることが重要です。しかし、そのような人材は現地では少なく、税務、労務、知的財産など各分野に精通した専門家とのネットワークを構築するのは容易ではありません。そのため、問題発生時に迅速に相談できる体制を整えるには時間と労力が必要です。
定期的な法的リスクの見直しと、予防的な法務対応を怠らないことが、限られた人材環境の中でも大きなトラブルを回避する鍵となります。
ベトナムでの経営運営における実務的課題
ベトナムでの事業運営では、日本とは異なる環境下での生産性向上や品質管理、コスト管理などの実務的課題に直面します。現地の実情に合わせた柔軟な対応が求められます。
現地調達率の低さとサプライヤーの品質・信頼性
ベトナムの製造業において大きな課題となっているのが、原材料や資材の現地調達率の低さです。多くの日系企業が日本からの輸入に依存しており、これがコスト増加や納期遅延の原因となっています。
現地調達率向上のためには、信頼できるサプライヤーの開拓が不可欠です。ただし、品質基準や納期管理において日本の基準との差異があることを前提とした取り組みが必要となります。
サプライヤー開拓においては、品質監査の実施や技術指導の提供など、現地企業の能力向上を支援するアプローチが長期的な成功につながります。また、複数のサプライヤーとの関係構築により、リスク分散を図ることも重要です。
生産効率と品質管理の不安定さ
日本の生産システムをそのままベトナムに導入しても、期待される効果が得られない場合があります。現地の設備環境、作業員のスキルレベル、文化的背景を考慮した最適化が必要です。
生産効率向上のためには、まず現地の実情を正確に把握することから始まります。作業プロセスの可視化と改善点の特定を行い、段階的な改善を進めることが効果的です。
品質管理においては、検査基準の明確化と作業員への徹底した教育が重要です。不良品発生の原因分析と再発防止策の実施により、安定した品質水準の維持が可能となります。
賃金上昇によるコスト圧迫
ベトナムでは毎年1月1日に最低賃金が改定され、継続的な賃金上昇が企業の収益性に影響を与えています。特に労働集約型の製造業では、人件費の増加が利益を圧迫する大きな要因となっています。
人件費上昇に対する対策として、生産性向上による単位あたりコストの削減が重要です。自動化や省力化技術の導入検討、作業効率の改善、多能工化の推進などの施策が効果的とされています。
また、従業員のモチベーション向上により生産性を高めるアプローチも重要です。成果に応じたインセンティブ制度の導入や、技能向上に対する適切な評価制度の構築により、賃金上昇を上回る生産性向上を実現することが可能です。
行政手続きとインフラ環境の課題
ベトナムでの事業運営において、行政手続きの複雑さとインフラ環境への対応は避けて通れない課題です。効率的な事業運営のためには、これらの実情を理解した上での対策が必要となります。
煩雑な行政手続きと地方格差
ベトナムの行政手続きは非常に煩雑で、投資契約局、労働局、税務局、税関など複数の機関での手続きが必要となります。さらに、地方行政や担当者によって対応が異なることが頻繁にあります。
手続きの効率化を図るためには、現地の行政手続きに精通したスタッフの確保が重要です。また、各行政機関との良好な関係構築により、スムーズな手続き進行が期待できます。
地方によって異なる対応への対策として、進出予定地域の行政機関との事前協議や、現地の行政書士などの専門家との連携が効果的です。手続きの遅延を想定したスケジュール管理も重要な要素となります。
インフラ格差による運営リスク
ベトナムのインフラ環境は都市部と地方部で大きな格差があります。電力供給の安定性、道路交通網、通信インフラなど、事業運営に直結する要素において地域差が顕著です。
製造業での進出を検討する場合、工業団地の選定が特に重要となります。バクザン省、バクニン省、ビンズオン省など、日系企業の集積が進んでいる地域では、比較的整備されたインフラ環境を期待できます。
立地選定においては、初期コストだけでなく、長期的な運営コストやリスクを総合的に評価することが重要です。停電対策、水質管理、廃棄物処理など、日本では当然と考えられるインフラサービスについても事前の確認が必要です。
税務手続きと優遇制度判断の専門対応の必要性
ベトナムの税制は非常に複雑であり、特にVAT(付加価値税)法をはじめとする各種税法の理解と適切な対応が求められます。さらに、外国投資に対する優遇制度が多く存在する一方で、これらの制度を誤って利用すると、税負担が不必要に増加するリスクもあるため、注意が必要です。また、税務申告ミスや不適切な申告によって罰金や追徴課税が発生し、企業の信頼にも影響を与える可能性があります。
税務手続きの適正化のためには、現地の税務専門家との連携が不可欠です。月次の税務申告から年次の税務調査対応まで、継続的なサポート体制の構築が重要となります。
投資優遇制度の活用においては、業種や投資規模、立地地域などの条件により異なる優遇措置が適用されます。事前の詳細な調査と申請手続きの適切な実施により、大幅な税制優遇を受けることが可能です。
まとめ
ベトナム進出における課題は多岐にわたりますが、適切な準備と対策により解決可能です。法規制の変化への対応、人材確保・育成、コンプライアンス体制の構築、実務的な運営課題の解決、行政手続きとインフラ環境への対応が主要な課題となります。
- 2025年の法改正により受益所有者登録など新たな規制への対応が求められる
- 管理者層の人材不足に対しては継続的な人材育成投資を実施する
- 現地スタッフのコンプライアンス意識向上と内部監査体制を強化する
- 現地サプライヤー開拓により資材調達率向上を図る
- 煩雑な行政手続きには専門家ネットワークを活用する
- インフラ環境を考慮した適切な立地選定を行う
ベトナム進出を成功させるためには、現地の実情を深く理解し、継続的な情報収集と柔軟な対応が不可欠です。特に展示会への出展は、現地市場の理解促進や有力なパートナー企業との出会いの機会となります。
株式会社ビッグビートは、海外展示会出展のサポートをしています。特に、タイやベトナムに現地法人を有しており、出展企画の立案から展示ブースの設営、コンパニオンをはじめとする運営スタッフの手配や管理に至るまで、日本の高い品質基準を維持したまま、現地からの迅速なサポートを提供することが可能です。