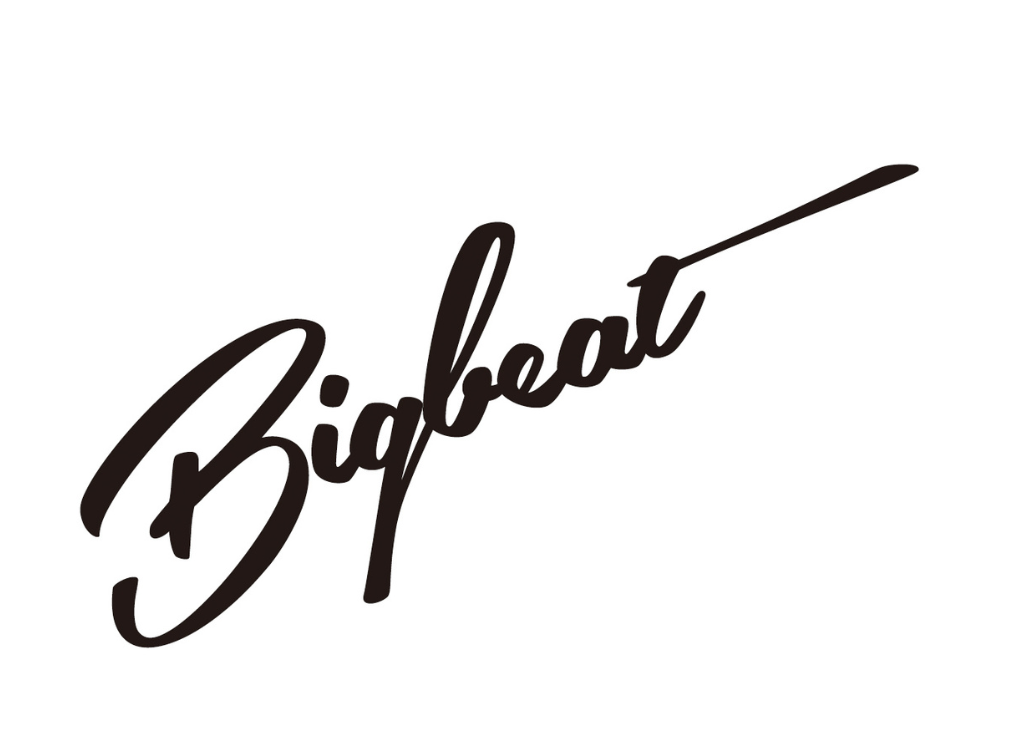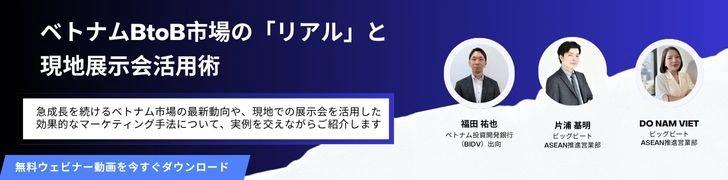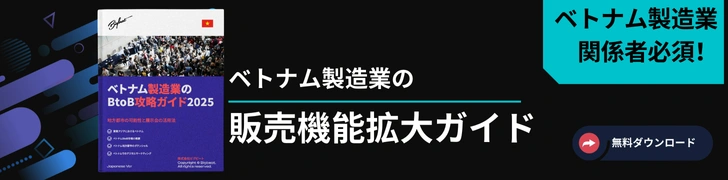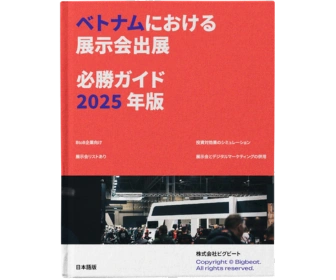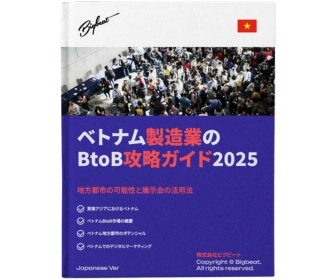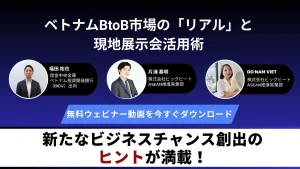ベトナムのFTAの全体像
ベトナムは東南アジアの中でも特に積極的に自由貿易協定を推進しており、2025年時点で多国間・二国間を合わせた包括的なFTA網を構築しています。これらのFTAは、関税削減だけでなく投資や知的財産権保護、公共調達といった幅広い分野をカバーする新世代型の協定となっています。
締結済みの主要FTA一覧
ベトナムが締結している主要なFTAは、多国間協定と二国間協定に大別されます。多国間協定には、ASEAN物品貿易協定を基礎としたASEAN+1協定群、包括的・先進的環太平洋パートナーシップ協定、地域的な包括的経済連携協定、欧州連合との自由貿易協定があります。
二国間協定では、韓国との自由貿易協定が2015年12月に発効しており、ASEANと韓国の協定と併存する形で活用されています。英国とのFTAは2021年1月に発効し、英国側の関税の65%が即時撤廃され、6年後には99%に拡大される予定です。さらに、ユーラシア経済連合とのFTA、そして2024年10月に署名されたアラブ首長国連邦との包括的経済連携協定など、ベトナムは地理的に多様な市場とのFTAネットワークを拡充しています。
協定の適用範囲
ベトナムのFTAは単なる関税削減協定にとどまらず、包括的な経済連携を目指す新世代型の内容となっています。物品貿易における関税撤廃や削減に加えてサービス貿易の自由化、投資保護、知的財産権の強化、政府調達市場の開放など多岐にわたる分野を対象としています。
特にEVFTA(EUとのFTA)やCPTPP(アジア太平洋地域12カ国とのFTA)などの新世代型FTAでは、地理的表示の保護や労働・環境基準の遵守、電子商取引に関する規定なども含まれています。また、非関税障壁の削減や手続き簡素化に関する規定も重要な要素であり、通関手続きの迅速化や透明性の向上により、実際のビジネス環境の改善につながっています。
関税撤廃のスケジュール
各FTAにおける関税撤廃のスケジュールは協定ごとに異なり、品目によっても段階的な削減期間が設定されています。CPTPPでは、加盟国の97%から100%の品目について対ベトナム輸入関税が撤廃される予定です。
EVFTAでは、発効から7年から10年をかけて段階的に関税が削減され、最終的にはEU側が99%、ベトナム側が約65%の品目で関税がゼロになります。即時撤廃される品目もあれば、10年以上の移行期間を設ける品目もあり、繊維製品や農産物などセンシティブな品目については慎重な段階設定がなされています。企業は自社製品がどのスケジュールに該当するかを把握し、中長期的な輸出戦略を立てることが重要です。
ベトナムが参加する主要なFTAの特徴
ベトナムが締結している主要なFTAは、それぞれ異なる特徴と戦略的意義を持っています。各協定の内容と活用方法を正しく理解することで、企業は最適な輸出入戦略を構築することができます。
ASEAN関連協定の特徴
ASEAN物品貿易協定は、ベトナムの貿易政策の基盤となる枠組みです。ASEAN10カ国間での関税削減・撤廃を進めており、域内の貿易円滑化に大きく寄与しています。
さらに、ASEANは日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランドとの間でASEAN+1協定を締結しており、これらの協定を通じてアジア太平洋地域との貿易が促進されています。ASEAN中国FTAやASEAN日本包括的経済連携協定などがこれに該当します。
ASEAN関連協定の特徴は、段階的な関税削減スケジュールと柔軟な原産地規則にあり、域内サプライチェーンの構築を後押ししています。
RCEPの構造
地域的な包括的経済連携協定(RCEP)は、ASEAN10カ国と日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドの15カ国が参加する大規模なFTAです。世界のGDPと貿易の約3割を占める経済圏を形成しており、ベトナムにとって戦略的に重要な協定となっています。
RCEPの大きな特徴は、統一された原産地規則と累積規定の明文化です。従来の二国間FTAでは各協定ごとに異なる原産地規則が適用されていましたが、RCEPでは域内共通の規則が適用されるため、企業の事務負担が軽減されます。累積規定により、複数のメンバー国由来の原材料を組み合わせて製造した製品でも、域内全体での付加価値として計算できる仕組みが整備されています。
RCEPの影響
世界銀行の分析によれば、RCEPによりベトナムは参加国の中で相対的に最大の恩恵を受ける見込みです。所得水準が基準線比で4.9%増加し、輸出が11.4%増、輸入が9.2%増という推計が示されています。電子機器や機械部品の生産では、日本や韓国からの高度な部材を輸入し、ベトナムで組み立てて域内外に輸出するビジネスモデルが拡大中です。
一方で、特恵関税の実際の利用率はまだ低い水準にとどまっています。報道によれば、RCEPの利用率は1.8%程度とされており、原産地規則の理解不足や社内手続きの整備が課題となっています。
EVFTAの適用状況
EUベトナム自由貿易協定(EVFTA)は、2020年8月に発効し、ベトナムにとって先進経済圏との初の包括的FTAとして注目されています。発効から5年間の累計双方向貿易額は約2,980億米ドルに達したとの業界団体の速報値があり、協定が貿易拡大に寄与していることが示されています。
EVFTAは関税撤廃だけでなく、地理的表示の保護、公共調達市場の開放、投資保護、知的財産権の強化など広範な分野をカバーする新世代型協定です。ただし、原産地規則の遵守と必要な証憑の整備が利用の前提条件となるため、企業は社内体制の構築が求められます。
日本・ベトナム間で利用可能なFTA
日本とベトナム間では、複数のFTAが併存しており、企業は案件ごとに最も有利な協定を選択できます。日本ベトナム経済連携協定は2009年に発効した二国間協定であり、長年にわたり日越貿易の基盤となってきました。
さらに、ASEANと日本の包括的経済連携協定、そしてCPTPPとRCEPという多国間協定も利用可能です。これらの協定は関税率や原産地規則、手続き要件が異なるため、複数の協定を比較検討し、関税優遇額と手続きコストのバランスを考慮して選択することが重要です。
FTAがベトナムの産業に与える影響
ベトナムのFTA網は、同国の産業構造と経済成長に多面的な影響を与えています。輸出産業の拡大、輸入品の多様化、国内産業の競争力強化、雇用創出など、さまざまな効果が観察されています。
輸出産業への効果
FTAによる関税削減・撤廃は、ベトナムの輸出産業に大きな恩恵をもたらしています。繊維・アパレル産業では、EVFTAやCPTPPの関税優遇により欧州や環太平洋市場での価格競争力が向上しました。電子機器や機械部品の輸出も拡大しています。RCEPの発効により、日本や韓国、中国からの部材を調達してベトナムで組み立て、域内外に輸出するサプライチェーンが効率化されました。
農水産物の輸出では、EVFTAによる地理的表示保護やEU市場へのアクセス改善が追い風となっています。コーヒーや水産物などの主力輸出品は、品質基準への適合を進めることで高付加価値市場への参入機会を得ています。
輸入の影響
FTAによる関税削減は、ベトナム企業にとって原材料や中間財の調達コスト低減につながっています。製造業では、高品質な部材や機械設備を低コストで輸入できるようになり、製品の品質向上と競争力強化が実現している状況です。
ただし、輸入の急増は国内産業への競争圧力となる側面もあり、政府は国内企業の競争力強化策と並行してFTA推進中です。特にセンシティブな農産物などでは、段階的な関税削減スケジュールを設定することで、国内生産者への影響を緩和する配慮がなされています。
国内産業の競争圧力
FTAによる市場開放は、ベトナムの国内産業に競争圧力をもたらしています。特に中小企業や地場企業は、外国製品との競争激化に直面しています。高品質で低価格の輸入品が増加することで、品質や効率性の向上を迫られる状況が生まれています。
しかし、この競争圧力は必ずしもネガティブな影響だけではありません。多くのベトナム企業は、品質管理の強化、技術革新、マーケティング戦略の見直しなどを通じて競争力を高めています。また、外資系企業の進出拡大により、地場企業がサプライチェーンに組み込まれる機会も増えています。
雇用への波及
FTAによる輸出産業の拡大は、ベトナムの雇用創出に大きく貢献しています。繊維・アパレル産業や電子機器組立産業では、大量の雇用が生まれており、特に若年労働者や女性の就業機会が拡大中です。製造業の成長は、物流、貿易事務、品質管理、マーケティングなど、さまざまな職種での雇用機会の創出にもつながります。
一方で、輸入競争の激化により一部の国内産業では雇用減少の懸念もある状況です。政府は職業訓練プログラムや産業転換支援策を通じて、労働者の新しい産業への円滑な移行を支援する取り組みを進めています。
賃金の変動
輸出産業の拡大と外資系企業の進出は、ベトナムの賃金水準に上昇圧力をもたらしています。特に製造業や専門職では、熟練労働者や高度人材の獲得競争が激化しており、賃金上昇が続いているのが現状です。
賃金上昇は労働者の生活水準向上につながる一方、企業にとっては生産コスト増加の要因となるため、生産性向上や自動化投資が重要な課題です。ベトナムは依然として周辺国と比較して競争力のある労働コストを維持していますが、長期的には高付加価値産業へのシフトが求められています。
ベトナムでFTAを活用するための実務ガイド
FTAの恩恵を実際に享受するためには、企業が適切な手続きを理解し実行することが不可欠です。ここでは、企業がFTAを効果的に活用するための実務的なポイントを解説します。
原産地証明の取得手順
原産地証明書は、輸出品がFTA締約国の原産品であることを証明する書類であり、輸入国での特恵関税適用に必要です。商工会議所が発行する原産地証明書と、一部の新世代型FTAで認められる認定輸出業者による自己証明の2つの方式があります。
商工会議所での取得手続きでは、まず企業が輸出製品の原産性を判定し、必要な証憑書類を準備します。部品表、製造工程記録、仕入先からの原産地証明などが必要となる場合があります。
EVFTAやCPTPPなどの協定では、認定輸出業者制度が導入されており、一定の要件を満たす企業は自ら原産地を証明する文書を作成できます。この制度を活用することで、迅速な輸出手続きが可能になり、ビジネスの効率性が向上します。
関税優遇の要件
FTAの特恵関税を適用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。最も基本的な要件は、製品が原産地規則を満たしていることです。前述のように、完全生産品であるか、実質的変更を受けた産品であることが求められます。
直送原則も重要な要件です。製品は原産国から輸入国へ直接輸送される必要があり、第三国での加工や積み替え時の規定を遵守しなければなりません。やむを得ず第三国を経由する場合は、税関の管理下にあることや再包装以上の作業を行わないことなどの条件があります。
認定輸出業者制度の活用法
認定輸出業者制度は、EVFTAやCPTPPなどの新世代型FTAで導入されている仕組みです。一定の基準を満たす企業が税関から認定を受けることで、自ら原産地を証明する文書を作成できるようになります。
認定を受けるためには、過去の輸出実績、コンプライアンス体制、原産地管理システムの整備などがベトナム税関に評価されます。認定輸出業者は、商工会議所を経由せずに原産地宣言を行えるため、手続きが迅速化し、コスト削減にもつながります。認定取得には時間がかかるため、計画的に準備を進めましょう。
ベトナムのビジネスには展示会出展が効果的
ベトナムでは、展示会への出展が企業のマーケティング戦略において極めて重要です。現地で開催される展示会は、自社の商品・サービスを認知してもらう最適な機会であり、特にB2B企業にとって欠かせない施策の一つとされています。開催数も年々増加しており、幅広い業種で行われる展示会は、効果的な販促チャネルとして注目されています。
展示会はテストマーケティングの場としても活用でき、現地顧客の反応を直接確かめることができます。さらに、単なる商品PRにとどまらず業界関係者とのネットワークづくりにも活用できるため、新規参入企業が現地での認知度を高め人脈を広げる上でも有効です。
このような対面での商談や交流を通じて有望な新規顧客の獲得やパートナー企業の発掘にもつながるため、展示会出展はベトナムにおけるB2Bビジネスで欠かせない施策となっています。
まとめ
ベトナムは多国間・二国間の包括的なFTA網を構築し、輸出拡大と経済成長を実現しています。各協定の特徴や原産地規則を理解し、適切に活用することで企業は大きなメリットを得ることができます。
- EVFTAやRCEP、CPTPPなど主要FTAが発効し、関税削減と市場アクセスが拡大している
- 原産地規則の遵守と累積規定の活用が特恵関税利用の鍵となる
- 繊維、電子機器、農産物など各産業でFTAの恩恵を享受している
- 原産地証明の取得手順と認定輸出業者制度を理解し実務に活用する
ベトナム市場への参入やビジネス拡大を検討している企業は、FTAの活用と並行して展示会出展などの現地マーケティング施策を組み合わせることが効果的です。株式会社ビッグビートは、海外展示会出展のサポートをしています。特に、タイやベトナムに現地法人を有しており、出展企画の立案から展示ブースの設営、コンパニオンをはじめとする運営スタッフの手配や管理に至るまで、日本の高い品質基準を維持したまま、現地からの迅速なサポートを提供することが可能です。